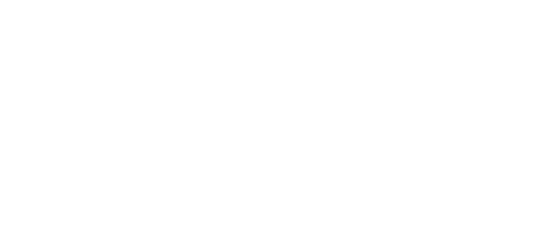前回まで種類株式について解説しましたが、似たことができる仕組みとして「属人的株式」があります。
1.定義
株主は株数に応じて平等に扱われるのが原則ですが、株主ごとに異なる取り扱いができる株式のことを言います。
つまり誰が持っているかによって株の性格が変わります。
2.内容
次の3つの権利について株主ごとに異なる内容を定めることができます。
・剰余金の配当を受ける権利
・残余財産の分配を受ける権利
・株主総会における議決権
配当や残余財産の分配については特定の株主を多く、あるいは少なくすることができます。
議決権についても、普通は株式数とイコールですが、特定の株主を増やしたり、逆に減らしたりすることができます。
<例:議決権>
・父 20株⇒父が持てば議決権10倍と設定⇒議決権200個(71.4%)
・子 80株⇒そのままなので議決権80個(28.6%)
財産としての株式は子が8割持っていますが、議決権で言うと父が2/3超で強い発言権を持っていることになります。
3.活用例
・事業承継時に先代経営者が影響力をキープできる(上記2の例)
・財産的には子ども3人に平等に株を分配しつつ、後継社長1人の議決権を増やして経営しやすくできる
・特定の株主に多く配当したい
発行方法や種類株式との違いについては次回へ続きます。