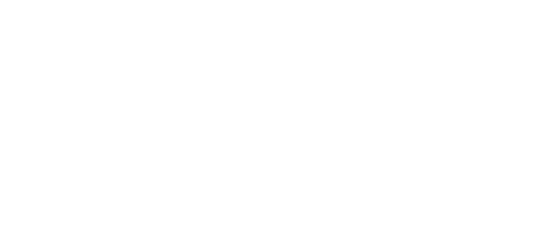前回の続きで種類株式の使い方について見ていきます。
1.単独での機能(比較的使われるもの)
・資金調達:① 配当優先株式(配当目的の株主の募集)
・会社運営:③ 議決権制限株式(決議しやすいよう発言権を限定)
・企業防衛:④ 拒否権付株式(自主性保護と買収への対抗策)
・株主限定:⑥ 譲渡制限株式(総会屋のような部外者を排除)
2.組み合わせでの活用例
9つの種類株式に関して、組み合わせることで事業承継にも活用されています。
<④ 拒否権付株式+⑦ 取得条項付株式>
会社の継続や相続税のことを考えると、株はなるべく早く後継者に渡して、社長も早めに交代したいところです。
しかし後継者の経営判断に不安が残るような場合に、先代社長が拒否権付株式を1株持つことで大きく間違った判断をした際にブレーキをかけることができます。
ただし拒否権付株式は強すぎるだけに、高齢で判断力が衰えた場合や亡くなった場合の相続など問題のタネになる可能性もあります。
そこで先代社長の死亡や後見開始など一定事由が生じた場合に会社が買い取れる取得条項付株式にしておけば、ソフトランディングが可能になります。
<① 配当優先株式+⑥ 議決権制限株式>
議決権制限で経営に口を出さない代わりに配当優先で多く配当をもらえるという組み合わせです。
配当を重視する株主から資金調達しやすいというメリットのほかに事業承継をスムーズに勧める手段にもなります。
例えば先代社長の配偶者や親戚などで経営にノータッチながら株を多く持っているようなケースがあります。
株主としては煩わしいこと抜きに配当さえもらえればいい、現社長としては不安定な株主に経営の主導権を握られることは避けたい、というような場合に議決権制限+配当優先にすることで双方にメリットが出てきます。
種類株式の相続税評価については次回へ続きます。