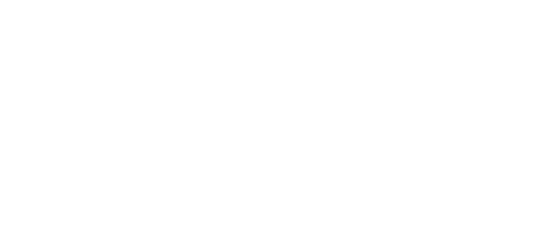前回の続きで103万円の壁がどう変わったかを見ていきます。
1.改正前
<そもそも103万円は何の数字?>
・年収103万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=0(本人の所得税0円)
※給与所得控除はサラリーマンに認められるみなし経費。最低55万円~最高195万円(子育て世帯等は210万円)
※基礎控除は生存権を保障するための最低限の生活費。全員にありますが、合計所得金額が2400万円超で減り始め、2500万円超で0円になります。
2.改正案
<基本ルール>
・給与所得控除:最低55万円⇒65万円
・基礎控除:48万円⇒95万円(48+10+37万円)
⇒95万円+65万円=160万円まで本人の所得税なし
<合計所得金額による違い>
① 所得132万円(給与200万円)以下…95万円
② 所得132万円超336万円(給与475万円)以下…88万円
③ 所得336万円超489万円(給与665万円)以下…68万円
④ 所得489万円超655万円(給与850万円)以下…63万円
⑤ 所得655万円超2350万円(給与2545万円)以下…58万円
<注意点>
・①は恒久措置、②~④は令和7、8年の2年限定、令和9年からは⑤の+10万円のみ
・現状からの上乗せは、①47万円、②40万円、③20万円、④15万円、⑤10万円、2350万円超は上乗せなし
・上乗せを段階的にした結果、おおよその減税効果は①2.4万円、②③2万円、④3万円、⑤2~4万円と年収による大きな違いはなし(単身者の場合)
・合計所得金額2350万円超の基礎控除は変わりませんが、給与所得控除は10万円増えるので僅かに減税にはなります。
所得税がかからない”103万円の壁”が160万円になったことでパッと見はそれなりの減税に見えますが、所得が増えるにつれ上乗せ額を削られ、850万円が事実上の上限となっています。
減税幅は国民民主案では7~8兆円と言われていましたが、今回の案では6200億円程度と1ケタ縮小しています。
(つづく)