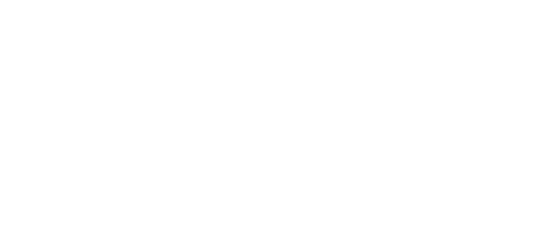前回の続きで配当控除について使うべきかどうかのポイントを見ていきます。
1.配当控除額
・通常の配当…10%(+住民税で2.8%)
・投資信託の分配金…5%(+住民税で1.4%)
・課税総所得金額等(総所得金額-所得控除)が1000万円超の場合はそれぞれ半分の割合
控除額の割合はかなり複雑ですが、主に出てくるパターンが上記の割合です。
2.条件
上場株の配当は20.315%の源泉徴収によって課税関係が完結しているので確定申告不要ですが、あえて申告して総合所得に含めることが配当控除を受けるための条件となります。
したがって他の所得も含めて何%で課税されているかによって有利不利が変わってきます。
① 課税所得330万円以下
(所得税10%-配当控除10%)+(住民税10%-配当控除2.8%)=7.2%
② ~課税所得695万円以下
(所得税20%-配当控除10%)+(住民税10%-配当控除2.8%)+復興税0.21%=17.41%
③ ~課税所得900万円以下
(所得税23%-配当控除10%)+(住民税10%-配当控除2.8%)+復興税0.273%=20.473%
①と②は源泉徴収される20.315%を下回っているので申告して配当控除を受けた方が有利です。
ところが③は税率が逆転するので申告せずに放っておく方がいいということになります。③以上の高い税率も同様です。
3.他の税金への影響
所得税と住民税の税率に関しては2で有利不利が計算できますが、申告することで他にも影響が出てきます。
上場株の配当は源泉分離課税なので、所得として「なかったもの」として扱われますが、確定申告すると所得に含まれるため、所得の多寡で判定する控除に影響が出ます。
・家族:扶養控除、配偶者控除(所得48万円以下)、配偶者特別控除(所得133万円以下)
・本人:配偶者控除、配偶者特別控除(所得1000万円以下)、ひとり親控除、寡婦控除(所得500万円以下)、基礎控除(所得2400万円以下)、住宅ローン控除、住宅取得資金贈与(所得2000万円以下)等
4.税金以外への影響
影響は税金だけに留まらず、健康保険等にも影響します。
・国民健康保険料 ※社会保険であれば影響なし
・介護保険料
・医療費の窓口負担割合
気にしだすと配当控除が使えなくなりそうですが、まずは2で税率の有利不利を判定して、3で扶養から外れないかどうか、4で健康保険料や介護保険料が上昇しないかどうかを考慮すればだいたいのケースには対応できます。