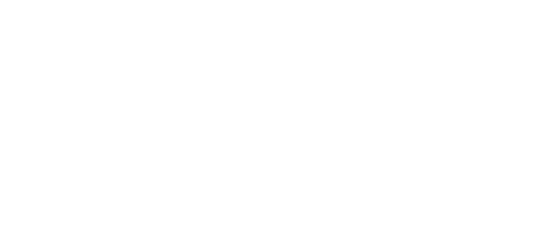非上場株式の評価方法について会計検査院が見直しを求めている、という記事が出ていました。
上場株式は日々株式市場の需給関係で株価が決まりますが、非上場株式は頻繁に売買されるようなものではないため、財産評価基本通達により相続税や贈与税で計算する上での評価額が定められています。
非上場株式の評価はまず2つに分かれます。
① 原則的評価:主要株主
② 例外的評価:少数株主⇒配当還元方式
主要株主については会社をコントロールできる立場にあるため、支配権をプレミアムとして評価します。
一方、少数株主は配当をもらうだけであまり口出しはできないので、もらった配当の額から評価します。
配当還元方式の方がかなり評価は安く、無配の場合は額面の半額になります。
主要株主の判定は大まかに言うと身内かどうかで判断しますが、甥姪や孫の妻などで、株数が少なく経営に関与していなければ、もはや株式評価上は他人同然と考えて、②の配当還元方式で評価できます。
原則的評価についてはさらに3つに分かれます。
A 純資産価額
B 類似業種比準価額
C AとBの併用
A 純資産価額
会社の決算書の純資産の部(資産-負債)をベースに評価します。
純資産の部には「資本金」と会社がそれまで積み上げてきた「利益」が蓄積されており、それが株主の財産ということになります。
なお資産については不動産や株式など買った金額より値上がりしているものもあるため、相続や贈与の時点で時価評価します。
含み益や含み損も考慮することで会社の正味の時価を計算します。
B 類似業種比準価額
類似業種比準価額とは類似する上場企業の株価を元に評価する方法です。
Aの純資産価額はその会社の状況だけから評価しますが、世の中の動きも反映させるのがBの類似業種比準価額です。
上場企業寄りの比較的大きな会社はこの方法で評価します。
C AとBの併用
小規模な会社はA、大規模な会社はBで評価しますが、中規模な会社はAとBをミックスさせて評価します。
ABCでどれが高くなるかは会社の状況や業界の状況にも寄りますが、一般的にはAが高く、Bが低い傾向にあります。
会計検査院の分析によると、AとBで約4倍の格差があり公平な評価方法とは言えない、と指摘しています。
税理士的には、実際に第3者に売れるわけでもないのにAの純資産価額は高すぎる、と言いたいところですが、会計検査院は格差のどちらを見直すべきかまでは言及していません。
線引きがある以上、なるべく評価が下がる方法を考えたくなりますが、会計検査院的には格差を利用した節税の動きも気に入らないようです。
どういう経緯で格差が生まれるか、逆に言うとどうすれば4倍の低い方で評価できるかについては次回へ続きます。