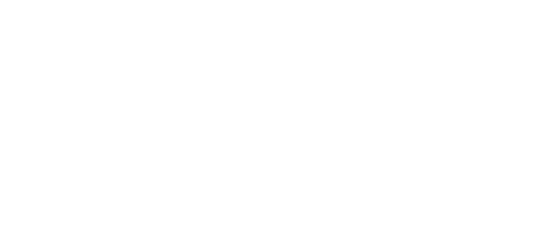前回の続きで下請法の内容について確認します。
<対象取引>
対象となるのは、既に存在している商品や市場で販売されていて誰でも買える商品を購入するといった取引ではなく、親事業者が事業として行っている製造工程を委託したり、受注した業務を外部に委託するといったものに限られます。
〇 メーカーが部品を部品メーカーに発注する
〇 出版社が原稿の執筆を依頼する
〇 システム会社が請け負ったプログラム開発の一部を外部委託する
✕ 自社HPのデザインを外部に委託する
✕ 受注した機械の製造を行うため、規格品のネジを購入する
✕ 弁護士や税理士への業務依頼
<区分>
下請法の対象範囲は、委託(外注)する取引の内容と資本金によって定められています。
➀ 物品の製造・修理、プログラムの作成、運送・物品の倉庫保管・情報処理
・自社の資本金が1000万円超3億円以下
⇒個人事業者、資本金1000万円以下の法人
・自社の資本金が3億円超
⇒個人事業者、資本金3億円以下の法人
② プログラム以外の番組・広告・デザイン・図面の作成、物品の運送保管以外のサービス(メンテナンス、コールセンター等)
・自社の資本金が1000万円超5000万円以下
⇒個人事業者、資本金1000万円以下の法人
・自社の資本金が5000万円超
⇒個人事業者、資本金5000万円以下の法人
親事業者に関しては義務と禁止行為が定められており、罰則もありますが、長くなるので次回へ続きます。