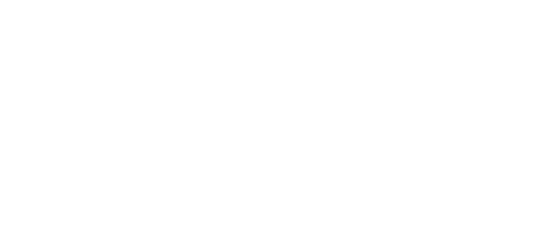相続があった場合には、相続人が協議して遺産を分割しますが、中には分けにくい財産もあります。
例えば遺産がほぼ自宅しかなくて相続人が子ども2人の場合、自宅を物理的に半々に分けることは困難です。
そこで兄が自宅を相続し、兄から弟に自分のお金を渡して半々になるように調整することがあります。
このような分け方を「代償分割」(代わりのもので償う)と言いますが、相続税や所得税の計算上注意すべき点があります。
注意点の前にまず4つの分割方法を整理します。
① 現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法。
例えば預金2000万円を1000万円ずつ分けるようなケースです。
手続き的にも簡単でオーソドックスな方法ですが、1筆の土地を現物分割する場合には測量や分筆が必要となります。
② 共有分割
土地や建物などを複数の名義で相続する方法。
平等に分けやすい点がメリットですが、後日売却、建築、借入などをする際には全員の同意が必要であるため、利用に制約が生じることがあります。
さらに代替わりが進むに連れて関係者が増えるため、より調整が難しくなります。
逆にすぐ売却する予定の不動産であれば共有のデメリットはさほどありません。
③ 換価分割
遺産を売却して現金化した上で分割する方法。
諸費用や税金を控除して残りを分ける形にすれば、いくらで売っても平等に分けられることがメリットです。
ただし、そもそも住んでいるから売れない、あるいは買い手がつかないといったこともあり得ます。
また売却に伴う譲渡所得が発生する場合にはその分手取りは減ることになります。
④ 代償分割
遺産を単独で相続した人が他に人に現金等を支払うことで精算する方法。
単独所有になるため、売却の手続きや売却後の確定申告などが進めやすいことがメリットです。
ただし、想定より高く売れた場合には結果的に代償金が少なかったということもあり得るので代償金の決定に難しさがあります。
長くなるので注意点については次回に続きます。