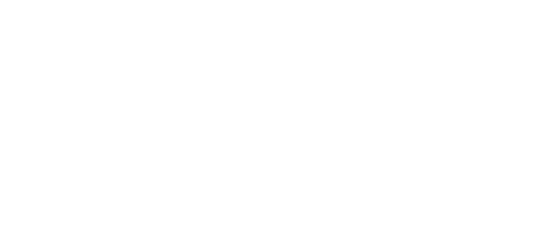年末調整の2回目は改正項目のメイン、定額減税です。
6月からスタートしていたのが「月次減税」、年末調整で実施するのが「年調減税」です。
月次減税の際に一通り解説しているので、月次と年調で異なる部分を中心に見ていきます。
1.対象者
① 月次
・令和6年6月1日現在勤務
・扶養親族分も令和6年6月1日時点で判定
・合計所得金額が1805万円を超える見込み(給料のみなら2000万円超)でも一旦強制的に減税
② 年調
・令和6年12月31日時点現在勤務(6/2以降入社なら年調で初めて減税)
・扶養親族分も令和6年12月31日時点で判定(月次で「源泉徴収に係る申告書」を提出して扶養を変更していれば再確認のために「年末調整に係る申告書」も要提出)
・給料2000万円超は年末調整自体できないので対象外
・給料が2000万円以下で他の所得を合わせると所得1805万円超となる見込みの人も対象外(月次減税している分はここで取り消されて徴収される)
2.控除方法
① 月次
・令和6年6月以後最初に支払う給料や賞与から減税
・引き切れない金額は7月以後12月まで順次控除
② 年調
・年末調整で減税
・引き切れなくても翌年への繰越はしない
3.書類作成
① 月次
・給与明細の中で減税額を表示
② 年調
<源泉徴収簿>
・右下の枠外余白に計算過程を記載
24-2 定額減税上限
24-3 減税後の所得税 → ×102.1%して枠内25欄に記載
24-4 控除しきれなかった定額減税額
<源泉徴収票>
・下の摘要欄に計算結果を記載
「源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇円」(実際に減税できた金額)
「控除外額 〇〇円」(控除し切れなった金額、0円でも記載)
・合計所得金額1000万円超で、同一生計配偶者の分を減税している場合は、摘要欄に「非控除対象配偶者減税有」と記載
本人の合計所得金額が1000万円超だと配偶者控除が使えませんが、配偶者の給料が103万円以下(合計所得金額48万円以下)なら定額減税だけは受けられるのでその旨を記載します。
・非控除対象配偶者が障害者の場合には短く「減税有」だけでOK(氏名等も書くので情報多いため)
・摘要欄には定額減税の情報を他に優先して記載
・年調減税していない場合(中途退職や給与2000万円超など)は摘要欄への記載は不要。月次減税した額も記載不要。