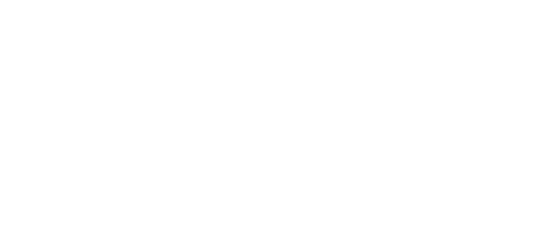掛金支払時、運用時、受取時と3段階で税が優遇されるiDeCo。
金融機関も力を入れているので普及しつつあります。
税に関することであまり取り上げられていないのがその”もらい方”
年金として受取る場合は「公的年金等控除」、一時金として受取る場合は「退職金」としての軽減があるのですが、この活用の仕方で税金は変わってきます。
<年金として受け取り>
国民年金や厚生年金と同じ扱いになり、公的年金控除が使えます。
年齢と受給額によって5~25%の控除があり、最低保障額は65歳未満なら70万円、65歳以上なら120万円あります。
iDeCoを受け取る場合、国民年金や厚生年金と合算して公的年金控除を計算します。
と言うことは厚生年金等とiDeCoの受給時期はできるだけ重複しない方がいいことになります。
iDeCoは原則60歳以降で支給時期を決められるので厚生年金等をもらえない、あるいは少ない時期に受け取る方が所得税は有利になります。
<一時金として受け取り>
退職金の税金は次の算式で計算します。
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率
① 退職所得控除
40万円×勤続年数(20年超は年間70万円、最低保障額は80万円)
② 1/2課税
役員が勤続5年以下で受け取る場合は1/2にはなりません。
③ 税率
他の所得と分離して所得税は5~45%の累進税率、住民税は10%。
ではこの退職金の税の仕組みがどう影響するのかという点は長くなるので次回に続きます。